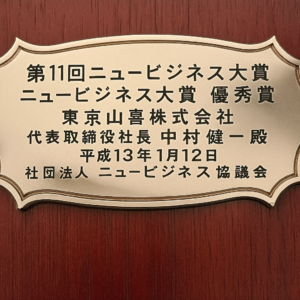満32才で取締役京都支店長に就任させて頂きました。場所は室町通り三条上る東側で、昭和62年(1987年)6月のことになります。祖父喜代蔵の創業の地が室町通り三条下る東側でしたから、ほど近い場所で、室町通り三条の北西角が、千吉の本社屋でした。この地は祇園祭りの役行者町で、千吉以外にも三京、阪本商事、グンゼ産業呉服販売などの著名着物メーカーが軒を連ねておりましたが、これらの着物メーカーも現在は廃業や移転などでこの地からは姿を消しております。祇園祭りで役行者町の山のお供をさせて頂いたのも、懐かしい思い出です。

東京の本社から離れた京都支店で部門長に就任させて頂き、私としては社長就任に向けてのステップと位置づけておりました。当時の京都支店のメンバーは支店長であった白井を含めてわずか3名で、これ以外に経理や営業補佐に女性が一人居るという状況です。
着任早々京都支店メンバーを集め、京都支店の4か年経営計画を立てて発表しました。「マメノキ」作戦です。マメノキは弊社の符丁で4、6、8、10という数字を表します。つまり、京都支店開設以来一度も年商2億円を超えられなかった売上を、一気に10億円に伸ばそうと言う計画で、特に初年度は1.8億円を4億円に伸ばすという相当無茶な計画でした。
当然ながらこの計画を実現する為には、新たな顧客、新たな商材、新たな企画、新たな人材が必要不可欠となります。新たな顧客では、従来の家業型専門店以外に、中国刺繍着物展示販売会を武器として、名古屋三越、だるまや西武、阿倍野近鉄、心斎橋そごう、高松三越、伊予鉄そごう、博多岩田屋はじめ多くの地域一番百貨店と口座開設をして頂きました。
それ以外にも、西日本の成長性のある大型着物専門店、難波の愛染蔵、名古屋のきもの錦、健勝苑グループ、たけうちグループ、ニッセンなどと次々にお取引を拡大していきました。私のザクッとした過去の記憶で恐縮ですが、これらの大型着物専門店は1990年台後半から2000年代前半に売上のピークを迎え愛染蔵約200億円、きもの錦約100億円、健勝苑約700億円、たけうち約600億円、ニッセンのユービスト事業部約100億円で、わずかこれらの5社の年商合計は約1,700億円にもなります。この金額は、現在の着物の市場規模約2,000億円の85%に匹敵する数字です。
従来は年商規模が数千万円から1億円前後の家業型専門店が中心でしたので、京都支店にとっては革命的変革でしたが、私の前任の支店長 白井は、店次長として、この短期間の変化に見事に対応してくれました。上記の西日本の成長性のある大型着物専門店の5社のうち健勝苑だけが現在も新健勝苑として存続しておりますが、残る3社と1事業部は消滅しています。
着任早々の昭和63年(1988年)1月に京都支店移転開設記念の大型販売会を企画しておりました。それは、4階建の新社屋に目一杯の商材を集中して、京都支店長着任の初年度から目標達成をするための販売会です。
これを成功させるべく、本社の専務清水と前年の秋から企画を練り、移転開設記念市用の商材集めに室町、西陣を奔走しました。その結果、私の京都支店長就任の御祝儀相場もあり、相当の商材が非常に好条件で仕入ができました。
専務の清水がこれだけの商品を京都支店のお客様だけにお見せするのではもったいない、本社の主力顧客の東京ますいわ屋の商品部長小沼さんをお呼びしようと言う事になりました。
当時の東京ますいわ屋は、全国に100店舗を超える業容で年商規模は約380億円でしたが、仕入は小沼部長が一人で見ておられました。やまとの年商規模は当時500億円を超えていましたが、アイテムごとに仕入担当者が分かれていましたので、おそらく当時一人で担当する仕入金額は業界に於いて断トツトップであったと思います。
正月の京都支店移転開設記念市に前もって、12月30日の仕事納めの日に小沼さんお一人の仕入のため、清水専務と京都支店全員でお迎えしました。初春の店頭販売のバーゲン商材として、現物を次々と仕入て頂き、約2時間の仕入が終わって手控えを集計したところ、9,000万円を超えていました。かつて経験をした事のない金額です。
清水専務は小沼部長を祇園にタクシーでご案内し、我々は仕入をしていただいた大量の着物と帯を佐川のチャーター便にその日のうちに積み込み、まさに仕事納めをさせて頂きました。
この東京ますいわ屋の小沼部長による京都支店年末特別仕入は、私が京都支店長を務めた4年間毎年の恒例になり、翌年は、1億円の大台に乗り、その翌年は11,000万円、最後の年は12,000万円になり、これらの売上は、本社計上でしたので、京都支店の売上には貢献しませんでしたが、京都支店の在庫活性化には大きく貢献してくれました。
また、2年目からは、私が中国で仕込んだ明綴帯が売上の底上げに大きく役立ちました。本当にありがたい仕入でしたが、なんと翌年本社に戻って常務取締役に就任した私が最初にくだした大きな決断が、この全社的超主力得意先との取引の中止でした。
その理由については、次回にさせて頂きます。