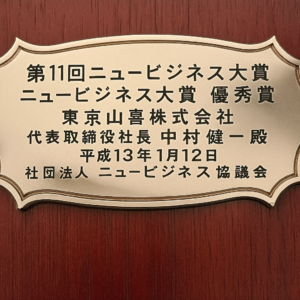7月16日水曜日、大阪・関西万博に行ってきました。昭和45年(1970年)の大阪万博に高校1年生で行って以来、55年振りの大阪万博です。岡本太郎の太陽の塔に代わるシンボルは大屋根リングだと思いますが、今でも鮮明に記憶している三波春夫の「世界の国からこんにちは」と比較すると、今回のオフィシャルテーマソングであるコブクロが歌う「この地球の続き」のインパクトは、残念ながら若干弱いように感じます。
当日の大阪の最高気温は約35°の猛暑日にもかかわらず、大勢の来場者で大賑わいで来場者の2,000万人突破が確実視されていますが、それでも前回の6,400万人には遠く及ばないのが現状です。国を挙げて一つのイベントに熱狂することが難しい時代背景を感じます。
かつては、堺屋太一の提唱する「イベント・オリエンテッド・ポリシー」に基づき、大阪万博のあと、昭和63年(1988年)の「奈良シルクロード博」、更に平成2年(1990年)の「大阪花博」が開催されました。
京都支店長に着任間もない折に「奈良シルクロード博」のオフィシャルスポンサーになり、春日野会場のオアシス物語館に「中国刺繍館」を出店させていただきました。15坪に満たない小さなブースでしたが、中国刺繍の着物や帯をメインに中国刺繍の小物や雑貨を品揃えし、183日間で約6,000万円を売り上げました。

これが自分が初めて小売を体験するきっかけになり、顧客のいない土地で小売経験のない呉服問屋が、年商に換算すれば1億2,000万円のショップを実現したことになります。粗利益率約70%、回収はすべて現金でしたので、オフィシャルスポンサーのフィーを差し引いてもしっかりと利益を残すことができました。
奈良シルクロード博のオフィシャルスポンサーの実績のおかげで、花博からもお声かけを頂戴し、こちらも出店させていただきました。これらの実績も含めて、平成3年(1991年)6月に4年ぶりに本社への帰還が内定しました。
当初の4年で京都支店の年商10億円は少し未達に終わりましたが、翌年、中国刺繍と東京手描き友禅、江戸小紋のメーカー事業部の「東美」が三条通り釜座のストークビルに発足し、一年遅れましたが京都支店と東美の売上合計で目標を達成することができたわけです。
本社に帰還する際、前もって父である喜久蔵社長に、「直近4年間の会社成長のエンジンは、京都支店の急成長がリードしておりました。本社への帰還を契機に代表取締役社長に就任させていただきたい。それが、本社の改革を最も容易にできるベストの施策と思います。」と訴えました。
喜久蔵社長の返答は、東京を4年も留守にしていた訳なので、いきなり社長に就任することはいかにも性急すぎる、せめて2年間は、常務取締役営業本部長として全社を見てからでも遅くないと説得されます。
言われることも全社的バランスを考慮すれば当然の判断ですので、逆に二年後の社長就任を密約していただくことで、常務として本社に復帰することになりました。満36歳の時のことです。
呉服問屋業にとって大きな経営課題の一つが与信管理でした。特にサイトの長い手形取引が取引形態の主流でしたので、得意先が経営破綻すると、多くの場合一年間の取引額程度の不良債権が発生することも珍しくありません。
私が本社に常務取締役として復帰した平成3年(1991年)はちょうどバブル崩壊のタイミングと同じです。当時の弊社の年商は約25億円でしたが、直近の売上の伸びのほとんどが京都支店の成長分でした。
そんな中、東京ますいわ屋とのお取引が急拡大していたわけです。要因は、京都支店開設記念の年末仕入を契機に、5月の弊社の本決算セールでも同様の仕入が定番化し、年末は京都支店で5月には本社で大口仕入の年二回が恒例化したことで、年間約2億円の買取仕入が定着することに。
加えて、奈良シルクロード博記念で、東京ますいわ屋の京都小倉山万葉苑における大型催事で第一室を任されたのをきっかけに、大型催事での売上も伸び、私が本社復帰時には、年商の一割を超える約3億円のお取引実績で、弊社にとって超主力得意先になっておりました。
天神橋筋5丁目時代からのご縁を考えると本当にありがたいことです。そんな中、私がいつも与信管理の情報源にしていた信用交換所の担当者から電話がありました。「未確認情報ですが明日、東京ますいわ屋さんが不渡を出します。」と言うものでした。
目の前が真っ暗になりました。同社の業績は決して悪くは無かったのですが、バブル崩壊で、海外不動産投資が焦げついたことが原因だと言うことです。
結果的にこの情報はガセで、通販大手のベルーナの子会社になった今日まで、同社は一度も不渡を出しておりません。しかしながら、常務取締役営業本部長に着任間もない私は、3億円近い不良債権を出した場合には、自社の経営基盤が揺らぐリスクを痛感し、即座に喜久蔵社長に同社とのお取引中止を進言しました。
社長も私の意見に同意してくれました。長いお取引と、ご愛顧頂いたご恩を考えると断腸の思いです。これが、私が本社に復帰し常務取締役営業本部長に着任後下した最初の経営判断でした。