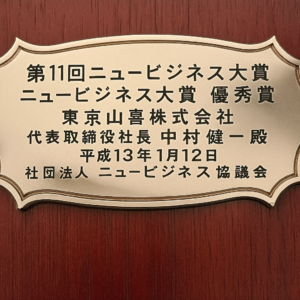社長就任以降、呉服問屋の三代目として、いろいろな模索をしてきました。
宝飾事業部は、従来の顧客、呉服専門店に、着物以外のアイテム、ジュエリーを催事で販売する手法を、多くの呉服問屋が手がけておりました。価格帯に親和性があり、呉服専門店に顧客名簿があり、ジュエリーメーカーの集客ノウハウを駆使すれば、目先が変わることで着物以上の売上を作ることが出来たのです。
しかしながら、販売チャネルを変えることで継続して呉服専門店でジュエリーが売れ続けることは容易ではないことは次第に実感することとなりました。宝飾事業部は、ジュエリーメーカーと提携して、無在庫で挑戦しておりましたので、見切りをつけて撤退することは比較的容易です。
次に中国での和装事業ですが、こちらは約10年に亘り弊社の収益力の原動力に大きく貢献してくれました。しかしここで実感したことは、中国で良いものを安く作っても、その恩恵は消費者には容易に届かないと言うもどかしさです。
着物市場がシュリンクしていく中で、売れる点数が減少するならば、利益幅を上げる方向に呉服問屋も、呉服専門店も向かう傾向が強まっていきました。ユニクロならば、自社で企画し、中国の協力工場で生産をし、自社店舗で販売するSPAですので、原材料コストや人件費の安さと中間マージンのカットで相当な価格訴求が可能ですが、着物市場の従来型流通ではその恩恵を消費者に届けることは至難の業です。
そこで、弊社の事業を根本的に改革するならば、着物市場でのSPAしかないと思うようになっていきました。その様な目で着物市場を見渡しても、SPAと呼べるモデルは皆無と言っていいほどの状況でした。
その様な凋落傾向にある着物市場で当時話題沸騰のブランドが、新装大橋が展開する「撫松庵」です。この「撫松庵」を銀座の松屋デパートで見た時に、ポリエステル素材ではありますが、これはこれで着物市場におけるSPAの成功事例の一つではと感じました。
その新装大橋が次に立ち上げたのが、リサイクルきもの「ながもち屋」で、これらのユニークなブランドは、新装大橋の大橋英士社長が発想し立ち上げたものです。大橋社長とは、江戸時代の小袖の復刻版を新装大橋から受注し、蘇州山喜有限公司で染めて刺繍加工し、裏地をつけて仕立て上げて納品させて頂いたご縁でお取引きができ、先輩経営者として親しくさせて頂いておりました。
そんなおり、衝撃的な着物の企画展が新宿の伊勢丹美術館で開催されました。「池田重子コレクション 日本のおしゃれ展」です。これはあくまで、着物コレクター、池田重子さん所有の着物や帯、和装小物を展示するだけで、販売会ではありません。入場料1,000円でしたが、来場者数は、当時の伊勢丹美術館の新記録であった「平山郁夫展」を凌駕したと記憶しております。
私も観に行きましたが、お客様の多さに圧倒されました。「着物はこんなにも多くの方々に愛されているのか!」と深い感銘を受けます。
着物市場でのSPAを模索するなか、「撫松庵」リサイクルきもの「ながもち屋」そして「池田重子コレクション 日本のおしゃれ展」の大盛況を目の当たりにして、自分の中で、リサイクルきものを中核に、独自の着物市場でのSPAモデルのイメージが育っていきました。
リサイクルきもの「ながもち屋」を研究していくと、そのビジネスモデルはコンサイメント、つまりお客様からお預かりした着物や帯を販売すると言うものです。
この時、偶然に荻窪駅の北口で出会ったのが、黎明期のブックオフでした。まだブックオフの存在を知らずに普通の新刊本屋と思い立ち寄ったのですが、あまりの繁盛ぶりに驚き、古本屋と知って二度びっくりします。私が知っていたのは、神保町に軒を並べた昭和からの古色蒼然とした古本屋でした。
何が違うのか調べてみると、ブックオフでは、買い取った本の表紙を洗剤で拭きとり、戸口を紙やすりで磨いていたそうです。これが大きなヒントとなります。
つまり「ながもち屋」のようにお預かりするのではなく、しっかりと買い取って、その後自社のリスクで、リファイン(丸洗い、殺菌、抗菌、消臭加工)をしたのち、自社店舗で販売すれば、リサイクルきもののSPAモデルが見えてくるように予感しました。そこに、中国で仕立て上げた新品の着物と帯を投入すれば、正絹の着物と帯をメインに着物市場でのSPAが実現するのではないかと考えるようになったわけです。
そこで、おおきなヒントを頂戴した新装大橋の大橋英士社長に自分の挑戦をお伝えしにいきます。『御社の「撫松庵」や「リサイクルきものながもち屋」にインスパイアされ、新たに、リサイクルきものショップ「たんす屋」を立ち上げたいと思っておりますので、よろしくおねがい致します。』とご挨拶させて頂きました。
すると、大橋英士社長からは、「良いところに目をつけられましたね、しかしながら、残念なことに、たんすの中にはもうすでに、良いお着物や帯はなくなってしまいました。気がつかれるのが、少し遅かったですね。」と言われます。
大橋英士社長は、本当にその様に思われたのか、私の挑戦を牽制されたのかはわかりませんが、私なりに筋は通したつもりでした。